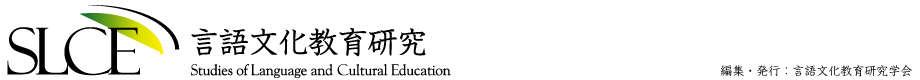論文
- 相互作用に関する考察―共有化に至る相互作用のプロセス
- 概要: 本稿では,相互作用の意義とその質的側面について考察する。具体的には,学習者4名を対象に,グループ内での相互作用を活動の基軸とし,自己の考えを明確にし,表現することによって,教室参加者が有機的に関わりあうことを目指した総合活動型日本語教育を実践しその活動を分析した。そして,相互作用の具体的なプロセスと,そのプロセスにおいてメンバーの間に作り出されたものについて検証を試みた。今回の分析では,相互作用の質の異なる3つの型の相互作用を抽出することができた。そのプロセスにおいて,メンバー同士の考えやレポートのテーマが共有化され相互的関係が築かれていくことが確認された。
- キーワード: 二方通行並列,制限された三方通行,完全な三方通行,共通性の発見,テーマの共有化
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]
- 言語能力はいかにして評価するべきか―ACTFL-OPI における言語能力観の分析と考察をとおして
- 概要: 本稿では,相互作用の意義とその質的側面について考察する。具体的には,学習者4名を対象に,グループ内での相互作用を活動の基軸とし,自己の考えを明確にし,表現することによって,教室参加者が有機的に関わりあうことを目指した総合活動型日本語教育を実践しその活動を分析した。そして,相互作用の具体的なプロセスと,そのプロセスにおいてメンバーの間に作り出されたものについて検証を試みた。今回の分析では,相互作用の質の異なる3つの型の相互作用を抽出することができた。そのプロセスにおいて,メンバー同士の考えやレポートのテーマが共有化され相互的関係が築かれていくことが確認された。
- キーワード: 二方通行並列,制限された三方通行,完全な三方通行,共通性の発見,テーマの共有化
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]
- 実践報告学校/教室という空間を超える試み―初級日本語における実践
- 概要: 本稿ではまず日本語教育で自明視されあまり振り返られることのない「学校」という空間についてもう一度見直し,カリキュラムの進度,授業形態,評価という問題点を指摘する。その後,その問題点を乗り越えるような多和の実践,ステップメソッドを紹介する。その実践では評価というものは学習者をレベルに振り分ける手段としてではなく,学習者がわかるということに結びつけるきっかけとしてとらえられており,様々な授業形態,また進度を調整することによって学習者の個人差にできるだけ対応している。
- キーワード: 学校文化,学習進度,授業形態,評価,学習者の個人差
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]
- 理解を検証する対話―対話において二人目の他者が持つ価値
- 概要: 理解の検証装置としてはどのような他者とのどのような対話が有効であるのかという問いに基づき,学習者と複数の他者との対話過程を分析した。その結果,ある他者が学習者に自分の意見をぶつけた時よりも,別の他者がその言葉を比較・相対化のために二次利用した時のほうが,学習者が理解を検証・更新しはじめる契機として有効である様子が抽出された。
- キーワード: 理解の検証,対話,第二の他者,比較,相対化
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]
- 日本語教育における自己を表現する力の育成について―「形式へのこだわり」意識の変容の考察を通して
- 概要: 本稿は「形式へのこだわり」意識の変容と自己表現力の獲得について考察することを目的とする。まず「形式へのこだわり」意識とはなにか,自己表現力とは何かについて論じることを試みる。次に,授業データ分析を通して,両者の関係性について考察する。
- キーワード: 「形式へのこだわり」意識,自己を表現する力
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]