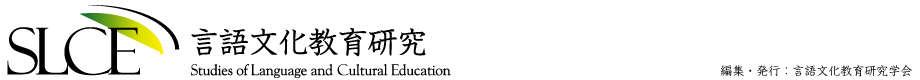論文
- 内在する思いを言語化する教室活動の効果と課題―自己把握・他者提示を中心とした対話型教室活動を観察して
- 概要: 本論文は,早稲田大学日本語教育研究科の実践研究の授業における,「総合活動型日本語クラス(総合)」の参与観察からの考察を述べるものである。観察から明らかになったことは,「総合」における自己把握と他者提示の繰り返しのプロセスは,学習者の内在する思いを引き出すとともに,日本語で自己の思いを言葉にして,他者とのやりとりをすることで,結果的に日本語での表現力を高めていく可能性があるということである。一方で,自己把握が進むほど,逆に他者提示が少なくなることも観察されたことから考えられる,対話型教室活動の課題についても併せて考察する。
- キーワード: 内在する思いの言語化,自己把握,他者提示,対話型教室活動
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]
- 教育=学びのための実践に向けて―「正しい日本語」観はどのような主体を構築しているか
- 概要: 「正しい日本語」観は日本語教育における教師/学習者の力関係にどのような機能を果たしているのであろうか。本稿では,まず,教育制度における「真理」が日本語教育では「正しい日本語」というイデオロギーとして機能し,その呼びかけに応じるように教師/学習者相互が従属化=主体化していくことを述べる。後半では従属化された主体とは別の主体を志向していくための「教育=学び」の可能性を論じていく。最後に従属化された主体とは別の主体性における学びの場として,個としての思考の場,他者との対話の場,文化リテラシーとしての学びの場を提唱する。
- キーワード: 正しい日本語,権力,呼びかけ,従属する主体,学びとしての教育実践
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]
- 日本語教育における「対話」アプローチの試み―触媒としての「文学」から「対話」を生成するコミュニティ設計
- 概要: 本論考は,JSL生徒の直面する問題を取り上げ,その解決方法として期待される『内容重視の日本語教育』がいかなるものかその内容を批判的に考察する。その上で「文学」という触媒をきっかけにして起こる「対話」アプローチの必要性を取り上げる。
- キーワード: JSL生徒,内容重視の日本語教育,「対話」アプローチ,触媒としての「文学」,「空所」と「否定」,「十人十色の文学教育」
- [早稲田大学リポジトリで閲覧]